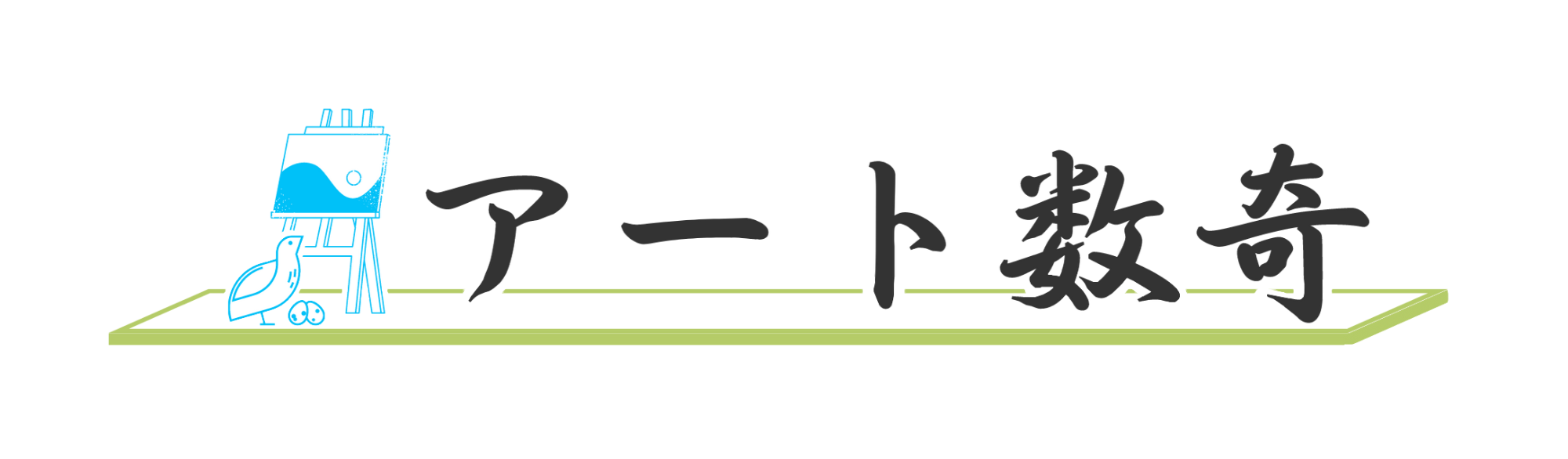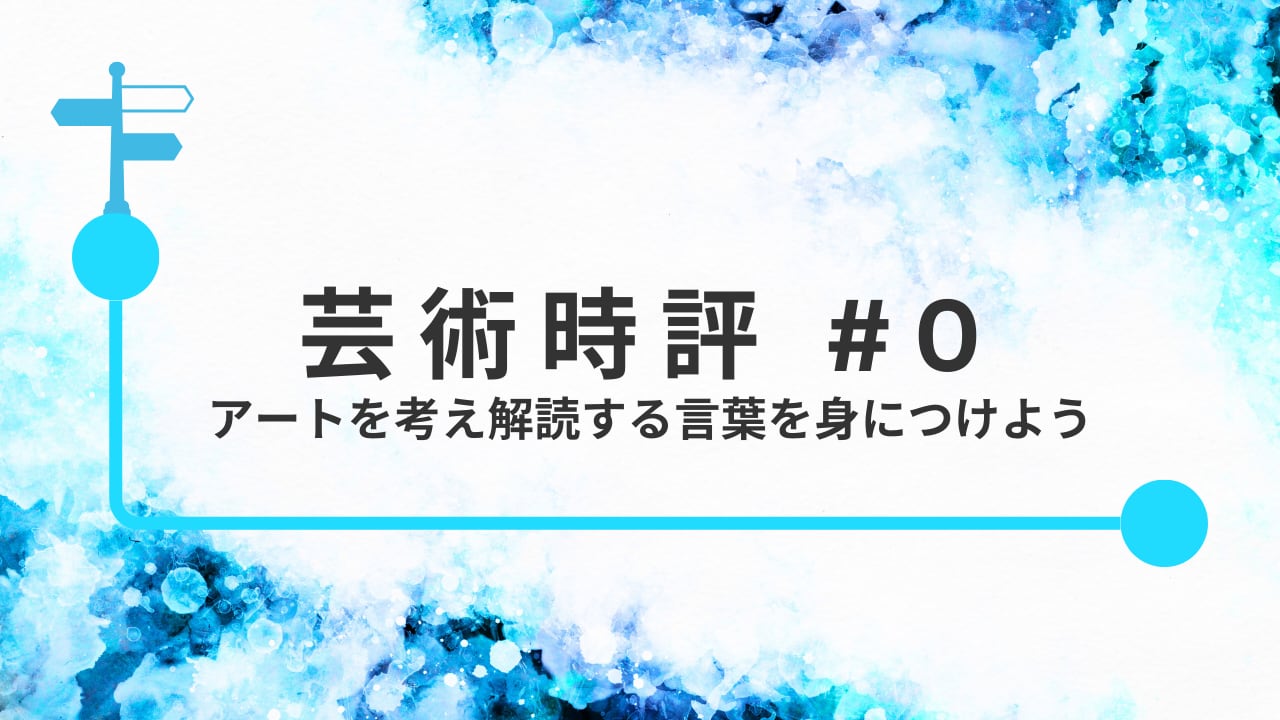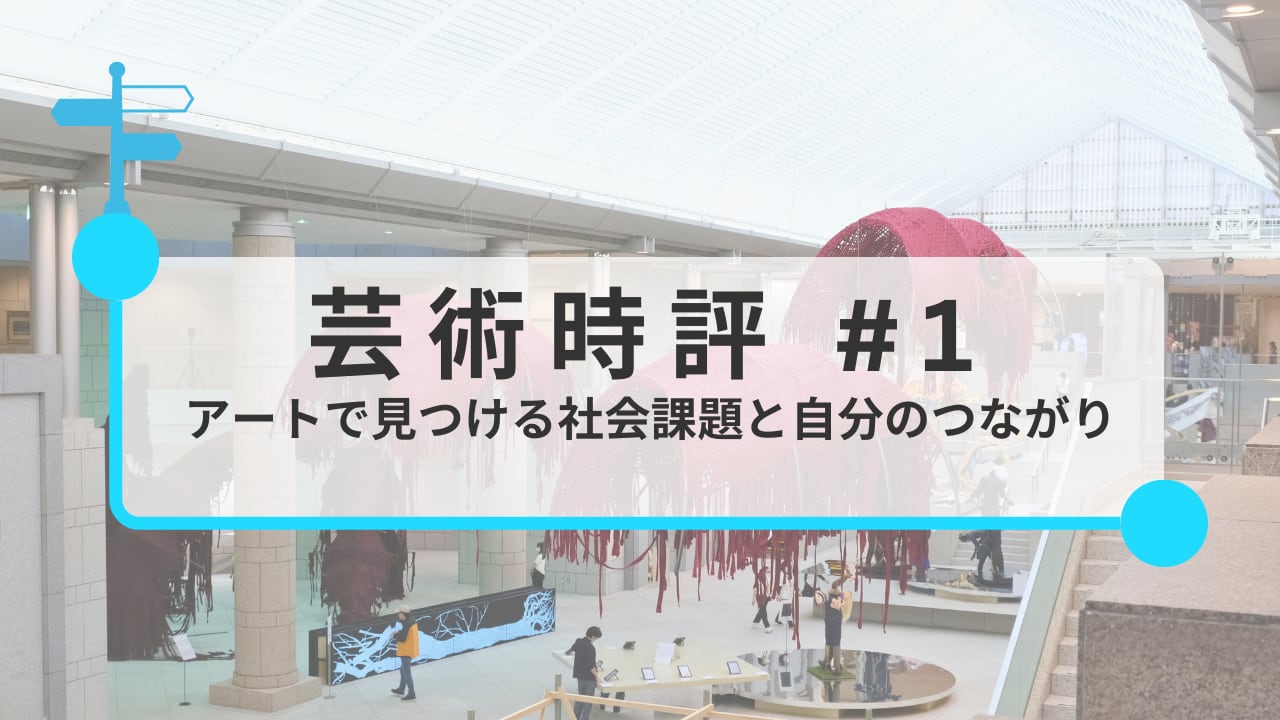アートを未来へつなぐための思考:作品保管から評価基準、文化支援まで|みなみしまの芸術時評#2〜夏のアート暑気払いレポート
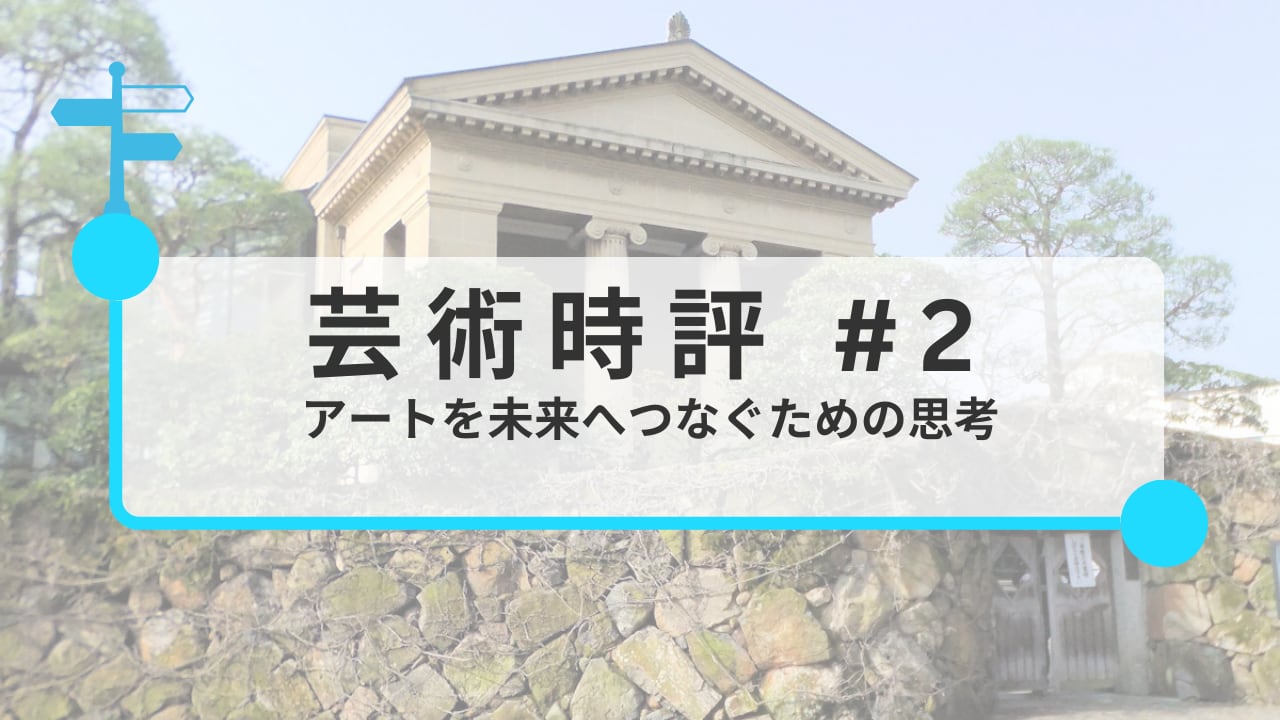
アート作品の多様な見方に輪郭を与え、解釈の道筋を示してくれる言葉。
観たことを言葉にできると、作品の持つ意味に近づけます。
そのための言葉を手に入れる方法の1つが、美術批評やレビューに触れてみること。
私自身、特に美術批評には慣れない言葉も多く難しさを感じていますが、言葉を何度も浴び続けてみると、作品を観る切り口が増えていく楽しさが生まれます。
その中でも初心者にも開かれた受け取りやすい言葉を浴びれるのが、社会と世界をつなぐアートの交通路をつくる「みなみしまの芸術時評」です。
今回は2024年8月10日に行われたサバービア・ラボ主催「みなみしまの芸術時評 #2〜夏のアート暑気払い」をレポートします。
今回まとめた芸術時評#2ではデジタル時代のアートのあり方や未来につなげていくための話題を中心に、
- 作品の保管問題とデジタルアーカイブの可能性
- アートと地域を繋いだ実業家・大原美術館設立者「大原孫三郎」
- 今月のアートブック4選
- コミュニケーションスペースを作る
- 美術館展示と評価について
の5つのトピックが紹介されました。
聞き慣れない言葉はできる限り分かりやすくなるよう意味を添えています。
芸術時評を通じて、アート作品を観るための言葉を採取していきましょう。

芸術時評とは何かについては#0のレポートをチェック。
書き手:よしてる
1993年生まれの会社員。2021年2月からオウンドメディア「アート数奇」を運営。東京を拠点に「アートの割り切れない楽しさ」を言語化した展覧会レビューや美術家インタビュー、作品購入方法、飾り方に関する記事を200以上掲載。2021年に初めてアートを購入(2025年6月時点でコレクションは30点ほど)。

作品の保管:実物かデジタルどちらを選ぶ?
芸術時評#2は、みなみしまさんの近況報告からスタートしました。
横浜美術館:リニューアル期間中も増えるコレクション
大規模工事のため3年間休館していた横浜美術館。
その間、収蔵作品たちはどうしていたのでしょうか。
工事が始まる前の2021年、収蔵作品約13,000点は外部倉庫に移送されていました。
工事終了後の2024年、横浜トリエンナーレを挟んで、外部倉庫に保管していた収蔵作品約14,000点を再度美術館に戻す作業を進めていたそうです。
ここまでで気づくのが、3年間で収蔵作品が約1,000点増えている事実。
横浜美術館は休館中の間も限られた予算の中で作品購入や寄贈、寄託によってコレクションを増やしていたそうです。
コレクションが増えることは、研究や展示の可能性が広がることを意味し、美術館にとって大事な要素です。
ここから話題は「作品の保管問題」に移ります。
作品の保管問題とデジタルアーカイブの可能性
作品の保管には「環境の整った場所の確保」「管理する人」「予算の確保」の3つが必要です。
いずれかが確保できなくなったときの対応策は以前から話題になってきましたが、芸術時評では直近でニュースとなった「民具のデジタル保存と破棄」について取り上げました。
作品の保管問題に関連するニュース「民具のデジタル保存と破棄」
1つ目が「奈良県立民俗博物館、約4万5000点の資料をデジタル保存へ(2024.7.30)|美術手帖」のニュース。
収蔵品の整理や施設の老朽化を理由に休館している奈良県立民俗博物館がデジタルアーカイブを導入し、物理的な資料の破棄を検討していることが取り上げられています。
2つ目が「日本民具学会が「民具(有形民俗文化財)の廃棄問題に対する声明」を発表(2024.7.22)|美術手帖」のニュース。
1つ目のニュースを受けて発表されたもので、声明では「民具が持つ群としての価値」と「次世代が価値を見出すことがあり得る」ことから、安易な破棄をすべきではないことが主張されています。
この2つのニュースをどう考えていくかについて話が展開されました。
歴史的な価値を保管していくには理屈が必要
声明の1つ目の論点では芸術作品と民具の性質的な違いが語られています。
- 芸術作品:優品主義、厳選主義、一点主義
- 民具:地域・時代を超えた比較研究から価値が見出される「群としての価値」
問題としては分かりやすく、連続的な記録に意味がある民具にとって、破棄されると比較研究ができなくなり、価値判断が難しくなる点があります。
問題は2つ目で、未来の同僚に賭けて保管継続する点は、物理的な取捨選択が求めれている今時点の判断は価値が分かっていない関係者でしなければいけない矛盾をはらんでいます。
この矛盾は美術館の作品収集とも重なるところがあり、価値が分からないものを残していくための理屈が必要になるといいます。
このロジックは作品を収集していき、それを研究し成果として展覧会を行う、美術館や博物館が持っているシステムが元々はらんでいる問題でもある。今必要なものを収集しているだけでは歴史を収集することにはならない。だから、今の我々にとっては意味が分からないものだが、きっと意味があるだろうと思えるものも収集し集積していくことで、いずれ価値を見出す人が現れることがある。
・・・今の価値観から言えばマイノリティにあたるものたちを収集していくことで歴史の全体像が見えてくるが、今の我々にとっては価値がないように見えている。これを、例えば行政に対しどう説明するかの理屈を作らないといけない。矛盾している時点で理屈は通らないが、それを通さないと歴史が記述されていかない、難しい状況がある。
デジタルアーカイブの可能性:未来に残すための新しい方法
歴史の保管にある問題の中で提案されている具体例が、デジタルアーカイブの導入です。
例えば、奈良県立民俗博物館の場合は約4万5000点の民俗資料を3Dデジタル保存する方針を打ち出しています。
一方で、2024年時点では実物を残す方に価値を感じる意見があるのも事実です。
相反する意見に対して、芸術時評ではデジタルアーカイブの可能性の例として、EBUNE(家船)の話題があがりました。
EBUNE(家船)と呼ばれる活動をしているアーティスト・KOURYOU(こうりょう)さんがいて、EBUNEの色んな活動をアーカイブするために自分でサイトを作っている。そのアーカイブ自体が一種の作品のようになっている。実体の活動とは全然違う形に編集されて、物語のような感じでウェブ上にアーカイブ作品が更新されている。
・・・データとしてウェブ上に沈没しているけど、いつかピックアップされる可能性に希望を見出すアーティストが今後現れても良いのでは。
(参考)EBUNEサイト:https://ebune.net/
EBUNEのサイトを見ると、誰でもアクセスできる状態で作品がアーカイブされています。
これまでは美術館への作品収蔵に価値を見出す人が多かった中で、今後はEBUNEのように、ウェブ上で生き残り続けるワイルドなデジタルアーカイブがあるときバズることで浮上し、認知される可能性もあります。
美術館のロジックでデジタルアーカイブをどう扱い、作品を手放していくかは今後も議論される問題としてありつつ、今アーティストが取る手段として自らウェブ上などの誰もが閲覧できる場でデジタルアーカイブをしていくこともあって良い発想です。
こうした問題は今後も出てくるので、2024年に決めてから数十年後に振り返り、答え合わせをしたときにどういう状況となっているのかが注目されます。
大原美術館設立者に見るアートと地域の関係性
大原美術館の設立者「大原孫三郎」は病院も作っていた
次の話題は、京都に村上隆さん「もののけ 京都」を見た後に、X経由で会った京都の書家からのすすめで、岡山・倉敷の大原美術館と「倉敷中央病院」へ行った時の話。
大原美術館は2023年にフランス近・現代美術の専門家である三浦篤(みうら あつし、1957 – )さんが館長に就任し、キュレーション展「異文化は共鳴するのか?」(2024)が開催されていたタイミングだったそう。
そして、キュレーション展を観たその足で向かったのが「倉敷中央病院」。
倉敷中央病院は「明るく温かく軽く柔らかく、住みよい住宅」のような病院を理想とし、現地にはステンドグラスや温室、アクアリウムなどの憩いの場所が多く設置されているのが特徴的です。
病院としては珍しい取り組みをしている倉敷中央病院の創設者も大原孫三郎さんなのが驚きです。
100年前の社会・文化支援が豊かな地域を醸成する
ここでひとつの疑問「美術館を作った人が病院も作ったのはなぜ?」が浮かびます。
そこには、大原孫三郎さんにとっては美術館も病院も、実業家として「労働者にとって理想的な環境を作る」観点でつながっていたことが挙げられます。
大原孫三郎さんはイギリスの説教家・ジョージ・ミュラー(George Müller、1805 – 1898)さんの影響で孤児院を始めた「児童福祉の父」と呼ばれるクリスチャンの石井十次(いしい じゅうじ、1865 – 1914)さんの活動に感銘を受け、独自の人格主義を育んだといいます。
そして「社会から得た富は社会に還元する」考えのもとに、労働環境の整備をはじめ、大原農業研究所、大原社会問題研究所、倉敷労働科学研究所、大原美術館などを設立しました。
こうした背景を踏まえると、大原美術館の設立が文化支援のためだけでないことが伺えます。
文化支援ではなく、極論をいったら「人々が住みやすい豊かな社会」を作るために投資をしている。その中の選択肢として病院や美術館があるのが正しい順序な気がしていて、そういう規模のパトロンっていうのはなかなか今日存在していない気がする。
・・・これは一種の労働者の環境改善運動で、その文脈の中で美術館ができている認識が重要。その意味で、倉敷は広い意味での文化芸術の都市であり、稀有な街。
・・・文化支援する前にそもそも人々の生活が豊かになることが普通にいわれることとしてあるが、それをマジでやろうとしたらこうなるはずだよっていうことを自でやっている。
社会支援のための投資をした大原孫三郎さんの生き様を知り、理想的な環境の中に必要な要素だったのが大原美術館だと知ると、美術館の見え方はもちろん、倉敷に設立した必然性も理解できて面白いです。
今月のアートブック4選
今月はライティング、美術批評、哲学的探究に関する新刊と、約50年前の「講演運動としてのサーカス」を紹介した本がピックアップされました。
今回は特にこの「サーカスが来た!」(1976初版発行、亀井俊介)がクローズアップされました。
今日イメージする娯楽としてのサーカスですが、かつてのアメリカには文化性の強い「知的な講演運動としてのサーカス」があったことが取り上げられています。
19世紀のアメリカには全国を巡りながら講演をする「さすらいの教師たち」と呼ばれる人達がいて、「一般大衆に向けて道徳的、知的な趣味を高める」地方文化向上の意図がみられたといいます。
そうした真面目そうな運動でしたが、教育と娯楽、説教とユーモアが結合し、次第に娯楽・ユーモアが優勢になったことで衰退したといいます。
講演としてのサーカスがあったこと、「娯楽の中にある教育性を保持していくコンテンツ」を考えていく方向性が面白く、みなみしまさんの活動とも関連性が高いことから、活動のリファレンス(参考)として延長線上にある希望を示している本としても紹介されました。
2つのアートフリートーク
フリートークでは「コミュニケーションスペースを作る」と「美術館での展示と作家の評価」について、ゆったりトークが展開されました。
コミュニケーションスペースを作る
まずは、みなみしまさんが関心を持っている「コミュニケーションスペースを作る」ことについて。
みなみしまさんは個人的な活動として、twitter上で芸術について語る配信や、時々DM相談会や電話相談会で見知らぬ人と話をするコミュニケーションスペースを開いています。
基本的な考え方として、芸術はコミュニケーションで回収できない非言語に触れるもので、「コミュニケーションスペースを作る」ことは芸術に関する活動とは対立しているような気がします。
ところが、7年ほどのtwitter上での活動を振り返った話を聞くと、一般的なコミュニケーションスペースとは異なる現象が起きていて、そのスペース自体がみなみしまさんの作家性が反映されている、一種の作品に思えてきます。
twitterで7年ぐらいほぼ誰も断らずに数百人ぐらいと直接会ったりオンラインで喋ったりしてきたが、全員才能があるとしか思えない人ばかりだった。
例えば、コラージュを作ってる人が陶芸もやっていたり、バイト先で号泣しながらDMしてくれた人が話していくと、みたいなことがあって、いい人しかいなかった。だから僕の結論は「twitterにはいい人しかいない」と言わざるおえないと思っている。しかし、それが一般的なtwitterの現実ではまったくない。
つまり、僕の「コミュニケーションスペースを作る」ではいろんなことをやっていて、それ自体が皆さんにとって意味が分からないもの、一般的なコミュニケーションの外側に存在している可能性がある。そこに皆さんとのズレがあり、僕のユニークさがあると思う。
「twitter = 炎上、否定的」な印象を持つ人にとって、「twitterにはいい人しかいない」は稀有な状態で、そうした場を生み出しているのはある種の非言語的な芸術と捉えられるかもしれません。
twitter上での「コミュニケーションスペース」をきっかけに見知らぬ人との対話が始まり、何かが動き始めた出来事を寄稿した「妄想講義」(2024)を読むと、よりリアルに、言葉をきっかけに非言語的な場が生まれていく様子が分かります。
美術館展示と作家の評価について
もう一つ話題となったのが、「美術館展示と作家の評価の関係性」。
以下の質問をきっかけに「美術館はどんな基準で作品を選んで展示しているのか」について話が展開されました。
. みなみしまさんは坂本夏子さんをどのように評価されていますでしょうか。
国立西洋美術館の「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」でも最後に出てきましたし、大原美術館の「異文化は共鳴するのか?」でも最後に出てくると思います。松方コレクションを元にしたキュレーションでも大原コレクションのキュレーションでも出てくるため、元々若手中堅で重要な人なんでしょうが、さらに重要な人物になってきている気がします。
坂本夏子さんは「一度描いたところには戻らない」といった描くことの方法論に対する強い意識を持ちながら、例えばタイル張りの密で異様な空間を絵画として生み出している画家です。
美術館のキュレーション展や収蔵もされている坂本夏子さんを取り上げつつ、「美術館での展示と作家の評価」について考えていきました。
作品の美術館展示、収蔵はどう決まる?
美術館の方針によって基準はさまざまですが、芸術時評では、
- 絵画が不要となった後に絵画を描く理由を問題として扱うこと
- 絵画の中で空間を表現する流れを汲んでいること
の2つの切り口が紹介されました。
1960年代以降くらいに絵画が不要となり、1970年代に宇佐見圭司(※)が絵を描く理由を探していた問題がおそらくあった。その問題と坂本さんの仕事が関係しているところがある。
また、(絵画の中に空間を表現することについて)空間がないところに空間を描くところから始まり、空間を別に読み替えていく挑戦が西洋美術史にはあった。
こうした「絵を描き始めるにはどうしたらいいか」問題と、古くからある「空間をどう表出するかの流れを汲んだ新しい表現をしている」の2つの交差点があり、どちらともが描かれている作品が美術館に好まれている気がする。
坂本夏子さんは空間を表出しようとしている意味では、クラシックな問題に取り組んでいる。クラシックな問題を自分の問題として、あるいは自分の身体的な問題として、あるいは自分が絵を描き続けるための問題として引き受けている部分が評価されていて、美術館に好まれやすいのかもしれない。特に、(美術館の都合もあるが)松方コレクションや大原コレクションのような伝統的な近代美術を中核に扱う美術館においては。
※宇佐見圭司(うさみ けいじ、1940 – 2012):画家・理論家。コンセプチュアル・アートの流行の中で絵画を描く意味が失われていた状況がもたらした事態を「失画症」と呼び、それに対して絵画を復興させる手だてを提唱した著書「絵画論」が有名。
良し悪しは別にして、美術館に好まれるジャンルがあり、絵画が歩んできた歴史や何を描いてきたかを汲んだ上で、新たな挑戦をしているところが評価につながっているのかもしれません。
今ある評価基準を解除する作品収集も必要
捉え方を変えると、美術館に好まれる評価基準は「今美術館にいる人にとっての評価」で、本当はその限界自体や条件自体を解除する可能性を考えることも必要です。
例えば、みなみしまさんが2000年代に生まれた画家と話した時に、空間を描こうとせず、「シンボル」を描こうとしていることに気づいたそうです。
人物画を描く場合、シンボルを操作(シンボルの持つ強さや情報の多さや不鮮明さから受け取れない状態にする、など)したり、シンボルの持つ象徴を支えている構造の解体をしたり、シンボルの人間性を取り戻すために物理的な筆触や筆致、ストローク、マテリアルなどの問題を扱ったりしていて、そこでは空間を主な問題として扱っていません。
こうした作品は美術館に好まれにくい一方で、評価方法を解除する可能性を持つものになるかもしれません。
これは「歴史を保管するか排除するかをどう判断するか」にも関連する話で、何を見据えた上での評価なのかを考えてみると、美術館に展示されている作品やコレクションの意味を紐解く切り口になりそうです。
まとめ:芸術時評でアートを読み解く切り口を発見しよう
今回の芸術時評では、デジタル時代のアートの在り方を中心に、「作品の保管」「文化支援の目的」「アートとコミュニケーションスペースの関係性」「美術館展示と評価」といった話題が取り上げられました。
それぞれの話は個人的な視点に落とし込んだ時に、作品購入や美術館での作品鑑賞の際にアートを読み解く切り口になります。
次回以降の芸術時評の配信もチェックしながら、アートを読み解く言葉を収集してみてください。